<ドナーについて>
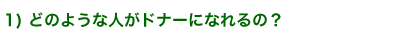
まず、ドナーの方に他者から強制されない自発的な提供の意思があることが大前提になります。基本的には3親等以内の親族(親子、兄弟、夫婦、祖父母、孫、叔父母、伯父母、甥、姪、曽祖父母、曽孫)及び配偶者ならば問題ありませんが、4親等以上の方では更に手続きが必要になります。日本移植学会の倫理指針によれば生体ドナーは親族に限るとされています。親族とは6親等以内の血族及び3親等以内の姻族のことをいいます。
年齢的には20才以上65才までの方で、基本的に健康な方に限ります。
血液型では輸血可能な組み合わせ(A型のドナーの方はA型・AB型の レシピエント、B型のドナーの方はB型・AB型、AB型のドナーの方はAB型のみ、O型の方はすべての血液型のレシピエントに)の方は提供が可能になります。それ以外の血液型の組み合わせでの肝移植は血液型不適合肝移植と呼び、つい最近までは移植後に激しい拒絶反応が起こるため移植後の成績は極めて不良でした。現在、特殊な免疫抑制剤の使用、および血漿交換などにより、血液型適合肝移植に近い成績となりました。しかしながら約3週間前からの術前処置が必要であるため、急性肝不全の患者さんには適応が難しいという制限があります。
白血球の血液型ともいわれるHLAの、あるタイプの方は提供が不可能なことがあります。
その他、血液検査や全身の検査で重篤な疾患のある方・悪性腫瘍のある方は提供できません。

外来での問診と血液検査及びCTなどの画像検査で判断します。画像検査ではコンピューターで肝臓の大きさを測定します。
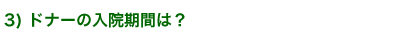
手術前3-7日と手術後平均2週間程度です。
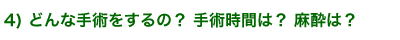
レシピエントが成人の方の場合、肝臓の左葉(全体の30-40%)あるいは右葉(全体の60-70%)を提供することになります。手術時間は約6−8時間で出血量は200-500ml程度です。輸血は基本的に必要ありませんが、出血時に備えて術前に自分の血液を400ml程度ためておきます(自己血貯血)。麻酔は全身麻酔で行います。全身麻酔に先立ち、痛みを軽減する目的で背中より硬膜外麻酔のチューブを留置し、術後の痛み止めとして用います。このチューブは通常術後2-3日目に抜去します。
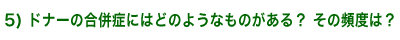
ドナーの方の安全確保は生体肝移植の最優先の課題です。しかしドナーの手術は肝臓を三分の一あるいは三分の二提供するという大きな手術で様々な合併症が起こりえます。全体でドナーの方の20〜30%に合併症が起こるといわれており、左葉より右葉を提供した場合の方が合併症の頻度が高いと言われています。具体的には創部の感染、肝臓切離面よりの胆汁漏、胃内容停滞、腸閉塞、胃・十二指腸潰瘍、胸水、脱毛症、上肢神経障害(手のしびれ)、声のかすれなどが挙げられます。これらの合併症は一過性のものがほとんどで、通常後遺症なく治癒します。しかし肺塞栓といった命にかかわる重篤な合併症も数例報告されています。わが国では、これまで5,000件以上の生体肝移植のうち、1例の死亡例が報告されています。
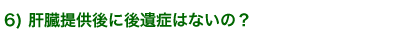
人によりスピードはまちまちですが時間がたつにつれ、次第に手術前の健康な状態に回復していきます。 我々の経験では、退院後はほとんどのドナーの方が術前と変わりなく生活されています。一部の方は傷の痛みやひきつれ・違和感・しびれ、食欲不振、疲れやすさを訴える方もありますが、永続的な後遺症が残ることはほとんどないといって良いでしょう。日本肝移植研究会が行った(→リンク:http://jlts.umin.ac.jp/)ドナーの追跡アンケート調査によれば、体調の回復はほぼ97%のかたが完全に回復(52.2%)あるいはほぼ回復(44.9%)と答えています。
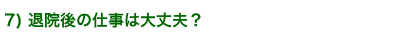
手術後2週間程度で退院し、術後3週間-1ヶ月程度で仕事に復帰することが可能ですが、自分の体調と相談して決めましょう。仕事が重労働の場合は主治医に相談してください。
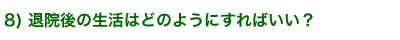
術後3ヶ月は創部の治癒が完全でありません。したがって術後3ヶ月までは重いものを持ったり、激しい運動をしたりするのは控えてください。その後は全く手術前と同じ生活・運動をしてもかまいません。食生活も以前と同じで結構です。
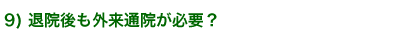
術後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、以後1年毎に外来で採血及び診察を行います。退院後は普通の生活に戻り定期検診のことを忘れがちです。必ず受診してください。

肝臓は再生力の非常に強い臓器で、したがって一部の肝臓の提供が可能になるわけです。大きさだけから言えば肝切除後、1ヶ月〜3ヶ月以内にほぼもとの大きさにもどることがわかっています。
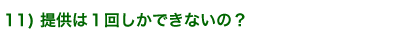
提供は1回のみで、2回目の提供はできません。
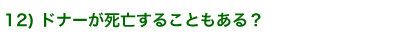
あります。わが国ではこれまで5,000件以上の生体肝移植がおこなわれてきましたがうち1人のドナーの方がなくなっています(0.02%)。全世界でも数件のドナーの方の死亡例が報告されています。したがって生体肝移植ドナー手術は100%安全とは言えないのが現状です。
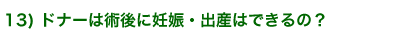
妊娠・出産は可能ですが、時期については主治医と相談しましょう。